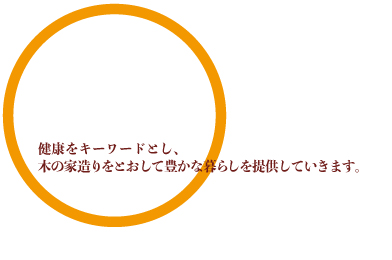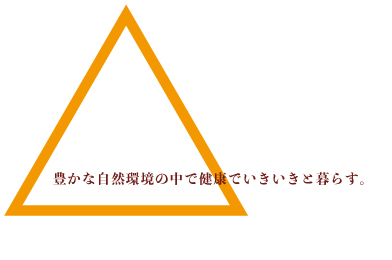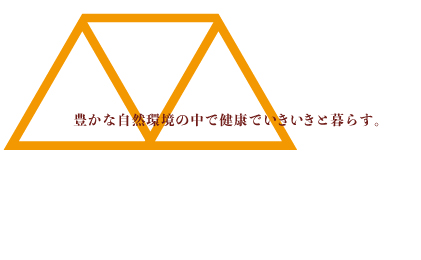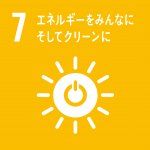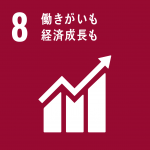私達そもん・らいふがどのような考えに基づいて家づくりを行っているか、
また、そもん・らいふが定義する「木の家(舎)」についてや、木の家で暮らすということをどのように捉えているかをご案内します。
創 造
「健康」をキーワードに日本の自然環境問題と高齢化社会問題に目を向け、多くの人々に健康で豊かな暮らしを提供していきます。
当社では「家造りは産業ではなく文化である」と考えています。ただ単に企業の利益を追求するのではなく独自の住宅文化を創造し、木の家造りを通して日本の文化に貢献していきます。
理 念
豊かな自然環境の中で、自然との共生、社会との共生、人との共生を大切に、そこに住む人の人生観に基づいて、健康で生き生きと暮らせる舎造り・・・。
日本は経済の高度成長の中、豊かな生活と引き換えに多くのものを失ってきました。
住宅造りもまた全国、地方、地域規模の大中小様々なハウスメーカーと 称される事業主体で 産業としての住宅造りが成されています。 住宅文化というには程遠く全国画一的な「商品としての住宅」が氾濫しています。そうした中での舎造りはどうあるべきでしょうか? 舎造りは物造りではなく、人生哲学としての個人の「こだわり」でありそして高温多湿の日本の気候風土の中で、長い間に培われ、自然淘汰され、地域の「こだわり」として生き残ってきたものが伝統文化なのです。
品 質
住宅の構造は大きく分けて木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造が考えられますが、高温多湿の日本の気候風土や歴史的背景からも木造が最適でしょう。
但し見掛けだけの木の家ではなく柱梁等の構造材を「あらわし」とした木の特性を生かした「ホンモノの木の舎」造りです。
しかしながら木をあらわしにすることはそう簡単なことではありません。木の良い特性である自然の気調 (断熱、調湿、浄化)をするといった事が建築品質の構造欠陥に繋がる事と表裏一体だからです。
それを補うには大工職人の手加工による「木組み架構」しかありません。
又、自然環境の維持の観点からいかにして国産材、地域材を使用するかは大変重要な問題です。
日本の林業が壊滅的状態にある今、全国津々浦々の地域の造り手、住まい手、そして一般市民が顔の見える関係を大切にした新しいネットワークを作らなければなりません。
人の和
職人の集団として
戦後70余年、家造りに於いても大工、左官、瓦、建具、指物、畳といった職人の技はほとんど失われようとしています。
わずかに50代60代の職人に引継がれている伝統の業も発揮する場もなく消え去ろうとしています。
今、ここで次の世代へどう継承していくかは大きな問題です。
ホンモノの木の舎造りを目指す当社にとってこうした職人の集団を造る事は必要不可欠です。
しかし其の事は簡単に短時間で出来る事ではありません。
但し何時までも手を拱いている時ではなく確たる計画をもって一歩ずつ前進すべく方策を取っていかなければなりません。
SDGsへの取り組みについて
「SDGs (エスディージーズ) 」とは、「Sustainable Development Goals (持続可能な開発発目標) 」の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の目標です。
- 当社では「家造は産業ではなく文化である」と考えています。ただ単に企業の利益を追求 するのではなく独自の住宅文化を創造し、木の家造りを通して日本の文化に貢献していきます。
- 高温多湿の日本の気候風土の中で、長い間に培われ、自然淘汰され、地域の「こだわり」として生き残ってきたものが伝統文化なのです。
目標2 飢餓をゼロに。
農林水産業は適切に機能すれば、すべての人に栄養豊富な食料を提供し、適正な所得を創出しつつ、人間中心の農村開発を支え、環境を守ることができます。
現状を見ると、私達の土壌や淡水、海洋、森林、そして生物多様性は急激に劣化しています。気候変動は、私達が依存する資源をさらに圧迫し、干ばつや洪水などの災害に関連するリスクを高めています。
目標3 あらゆる年齢のすべての人々の健康な生活を確保し、福祉を推進する。
あらゆる年齢のすべての人々に健康で生活を確保し、福祉を推進すことは持続可能な開発に欠かせません。
- 「健康」をキーワードに日本の自然環境問題と高齢化社会に目を向け、多くの人々に健康で豊かな暮らしを提供していきます。
- 地域の自然環境は地域で守らなければなりません。近くの山の木で家をつくることによって、その地域の森林を生かし、その町の環境を守ろうというのです。それがやがてこの国に自国の資源を持続して使える経済社会と、再び新しい豊かな木の文化をもたらしてくれるに違いありません。
- 自然環境の維持の観点からいかにして国産材、地域材を使用するかは大変重要な問題です。
日本の林業が壊滅的状態にある今、全国津々浦々の地域の造り手、住まい手、そして一般 市民が顔の見える関係を大切にした新しいネットワークを作らなければなりません。
目標7手ごろで信頼でき、持続可能且つ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する。
再生可能エネルギーの利用拡大に注力する事は、より持続可能で包摂的なコミュニティーをつくり、気候変動をはじめとする環境問題に対するレジリエンスを高めるうえで欠かせません。
目標13 気候変動とその影響に立ち向かう為、緊急対策を取る。
気候変動は、あらゆる大陸のあらゆる国に影響を与えています。気象パターンは変化し、海面は上昇し、異常気象はますます激しくなり、温室効果ガスの排出量は現在、史上最高水準に達しています。
目標15 森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止及び逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る。
地球の表面積の30.7 %を覆う森林は、食料の安定確保と住処の提供の他、気候変動との闘いや、生物多様性と先住民の居住地の保護にも鍵を握る役割を果たします。私達は森林を保護する事により、天然資源の管理を強化し、土地生産性を高める事もできます。

- 生き方、暮らし方といった観点からの家造りが大切です。「自分らしくどう生きるか」そ して「自然の中で健康な生活をする」といった価値観での家造りです。
- 人間は動物です。暑さ寒さに対応し、免疫力を高め動物としての機能を損なわない様にしなければなりません。極力エアコンに頼らず健康に暮らす事が重要です。
- こうした自然との共生を大切にした観点に立った時、高温多湿な日本の気候風土や歴史的文化的背景からも木造が最適でしょう。自然の気調(断熱、調湿、浄化)をするといった木の特性を生かした「ホンモノの」の家造りです。
- 健康で生き生きと暮らす薪ストーブのある木の家!
自然環境を大切に、健康を第一に考えた家造り。
地域の無垢材を使用し、大工職人の「てきざみ」により、構造材を「あらわし」とした木組み架構の家造り。 - 薪ストーブのある木の家で暮らす!
勿論二酸化炭素の排出の削減、そして森の活性化等大切な事もあるが、何と言っても心まで温かくなる心地良さ、灯りを消してゆらゆら燃える火を見て、パチパチ燃える音を耳にしてグラスをかたむける、最高です!
但し薪ストーブは単なる暖房機ではありません。
- 体を動かすことの少ない現代社会の中で健康の為に汗をかいて薪を作る。
- 親子で力を合わせて家の為の仕事として薪作りをする。
- それぞれの部屋ではなく自然に家族が薪ストーブの廻りに集まってくる。
そんな生き方、暮らしの一部としての薪ストーブなのです。

目標8すべての人々の為の包摂的且つ持続可能な経済成長、雇用及びディーセント・ワークを推進する。
持続可能な経済成長を遂げるためには、経済を刺激し、且つ環境に害を及ぼさない質の高い仕事に人々が就ける条件を整備する事が必要になります。雇用機会とディーセントな雇用環境は現役世代の人々すべてにとって重要です。
目標12 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
持続可能な消費と生産とは、資源効率と省エネの促進、そして基本的サービスと環境に優しく働きがいのある人間らしい仕事の提供、全ての人々の生活の質的改善を意味します。
持続可能な消費と生産は「より少ないものでより多く、よりよく」を目指しているため、経済活動による正味の福祉向上は、ライフサイクル全体を通じて資源の利用、劣化及び汚染を減らす一方で、生活の質を高める事によって促進できます。又、生産者から最終消費者まで、あらゆる人を巻き込みながら、サプライチェーン運用を大いに重視する必要も有ります。その中には、持続可能な消費とライフスタイルに付いて消費者を教育する事、基準やラベルを通じて十分な情報を提供する事、持続可能な公的調達に参画する事なども含まれます。
目標17 持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する。
持続可能な開発開発アジェンダを成功に導くためには、各国政府と民間セクター、市民社会のパートナーシップが必要です。原則と価値観、共有のビジョン、そして人間と地球を中心に据えた共有の目標に基づく包摂的なパートナーシップが、グローバル、地域、国内、地方の各レベルで必要とされています。
- 職人の技術を生かし地域でつくる!
モノをつくるのは結局人だという事です。大工職人や左官職人等それぞれのパートを受け持つ人が最後まで責任を持った仕事をするしか良い家を造る方法は無いのです。
再び自然素材で家を造ろういうのなら、人がモノと関わる経験を通して得た知恵と技術が不可欠です。木という自然素材を造る側の合理性でねじ伏せるのではなく、人が自然の持つ合理性に合わせて利用する事です。 - 今、木の家をどうつくるか?
モノをつくる仕事は本来、単なる労働とは違う達成感があるはずです。これは仕事の苦労を通して得られる満足です。
職人の誇りもまたここから生まれます。利潤の為の合理性だけではなく人が働く事、生きる満足をも含めた新しい木の家造りのシステムが求められています。
ただ伝統的構法に帰ろうという事ではなく、現代の新しい人とモノ造りのシステムを作り出すことを意味します。
何か新しい大掛かりな組織をつくる事ではありません。全国津々浦々の地域の林業家、製材所、大工職人、設計者、住まい手、一般市民が顔の見える関係を大切にした新しい家づくりのネットワークをつくるのです。 - 木の家造りのもう一つの大切な事は、如何にメンテナンスをしていくかです。
勿論「瑕疵」に対する会社の責任は当然ですが、其の事とは別に、木の家造の良さを維持管理していく事の大切さをしっかりと認識していく事への活動も大きな使命です。
目標11 都市を包摂的、安全、レジリエント且つ持続可能にする
雇用と豊かさを生み出しながら、土地や資源に負担をかけない様に都市を維持する為には、多くの課題が存在します。共通にみられる都市問題としては過密、基本的サービスを提供する為の資金欠如、適切な住宅の不足、インフラの劣化、都市内部の大気汚染の悪化があげられます。
- ふれあい健康ブィレッジ開発基本構想
福祉社会とは、市民がセキュリティーシステムが具わった安全で安心できる地域社会を確立し、健康で明るい生活の営みができるコミュニティーを形成する事が本来の姿であると 考えます。こうした観点から、環境保全型農業を基軸とした「豊かな自然環境の中で健康で生き生きと暮らせる」を街づくりの理念として、「歳をとっても安心して暮らせる」福祉地域を形成することを目的として出発します。こうした地域の形成には、民間のビジネスノウハウと運営ノウハウ、そして行政の様々な支援も必要です。