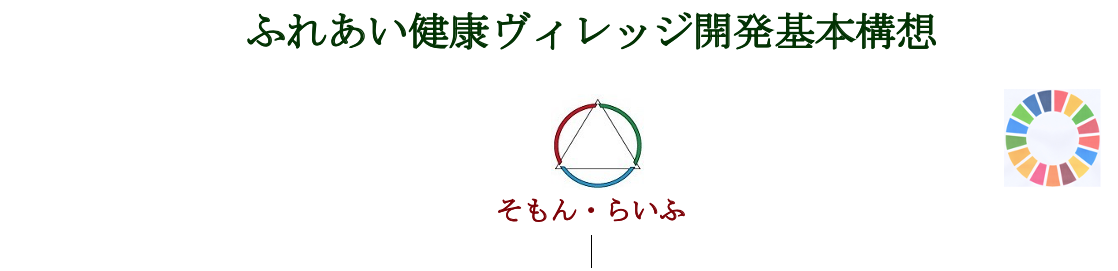開発事業推進協議会の目的趣旨
現在、全国に様々な福祉施設が計画・設立されています。この様な流れは行政が主体となった計画と民間が主体となった計画に大別2区分できますが、全体的に福祉社会の形成といった姿には程遠く、理念・全体像・将来を見据えた長期のそして順序を踏まえた段階的な計画性の見えない、場当たり的な、部分的な事業の感がする。
福祉社会とは、市民がセキュリティーシステムが具わった安全で安心できる地域社会を確立し、健康で明るい生活の営みができるコミュニティーを形成することが本来の姿であると考えます。
本計画はこうした観点から、環境保全型農業を基軸とした「豊かな自然環境の中で健康で生き生きと暮らせる」を街づくりの理念として、「歳をとっても安心して暮らせる」福祉地域を形成することを目的として出発します。こうした地域の形成には、民間のビジネスノウハウと運営ノウハウ、そして行政の様々な支援も必要です。
街づくりは市民が主となってすべきことであり、民間発意として出発した開発事業推進協議会を民間主体で構成して進めます。特に福祉といった分野は本来行政が主体となり民間に協力を依頼するのが一般的ですが、本計画の進め方としては民間主体で進め、行政とのコンセンサスを得ながら行政と民間の協力的な事業へと進めて行きたいと考えています。
本計画の目的
計画の狙い
戦後70余年、日本は経済の高度成長の中、豊かな生活と引き換えに多くのものを失ってきました。農業、林業、漁業といった一次産業が衰退し、乱開発により自然 環破壊が進み、二酸化炭素による地球温暖化が懸念されています。又一方で社会 福祉がおざなりにされ特に少子高齢化による高齢者福祉が大きな問題となって います。
こうした中で今、日本は豊かさの価値観が「もの」から「こころ」へと変わりつつあります。自然環境と高齢化社会に目が向けられ、ロハスという生き方の価値観に関心がよせられ、健康で豊かな暮らしを多くの人々が求めています。
福祉型事業は従来、民間事業に於いては限られたターゲット層(高所得者層) についてのみ成立する事業として位置付けられてきたが、厚生労働省の在宅介護保険法(新ゴールドプランの一環として)の法制化や国土交通省のケア付き住宅等の民間施設への補助金の導入等、福祉に対する社会基盤システムが充実しつつある現在、中間層・低所得者層を含む福祉ビジネスとして成立する時に至っている。
本計画はこうした状況の中で高齢化社会に対応した新たなるシルバー産業を構築し、高齢化地域の街づくりの中で中核的な先駆的事業として位置付け、開発していく。
もう一つの「豊かな自然環境の中で健康で生き生きと暮らせる」福祉地域を形成する目的として、この地域での緑豊かな自然環境の保全に対する一般市民の関心を高めることはもちろんのこと、農業の健全化が最も大切な事でしょう。しかしながら農業の後継者不足は今後の大きな課題です。
同時に団塊の世代と言われる人口の一番多い世代が60歳定年を迎えています。
企業戦士として経済至上主義時代を生きてきた世代の「健康と老後に対する不安の解消」として、そして「第二の人生に対する安心と生きがいの場」として「移り住むシステム」の構築と自然の中での「農業従事システム」を構築することが大切と考えます。そのことにより、農業の健全化を通して失われた地域の自然環境の回復と保全を図れるでしょう。
計画の早急性
本計画及び事業を進めるにあたり、いくつかの課題が想定できる。
- 用地の収得又は借り上げ。
- 市街化調整区域の解除。
- インフラの整備。
- 開発部の法的制限の解除
等々。
- 農業の後継者問題が急がれ、農地、森林の荒廃が日々進んでいる。
- 2007年から団塊世代が定年をむかえている。
- 住宅政策のテーマが良質な住宅ストックの形成と活用に転換し、2006年に住生活基本法が成立して構造的転換がなされてきた。
- 国土交通省の支援する「移住・住みかえ支援機構」が2006年10月から協賛企業の募集を開始した。この「住みかえ型リバースモーゲージ」は同省が創設した「高齢者の移住・住みかえ支援制度」により設立されたものでモデル事業として立ち上げ、バックアップしている。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律も改正され新たな登録制度が実施され「サ ービス付き高齢者向け住宅」の登録件数も増えている。
計画の趣旨
・事業は実現性も踏まえ適正規模と適正用途として実施する。
・計画は段階的に見直し、検討する。
・福祉をビジネスの中心に据えたケアーとセキュリティーの完備した街を構築する。福祉に対応する施設としてはケアハウス,サービス付き高齢者向け住宅等の施設と健康増進施設としてクラインガルテン等の施設が完備した福祉・健康増進の福祉先進事例をつくる。
・高齢者といってもひとくくりに考えるべきではないでしょう。ここでは60歳~75歳までを対象とした健康で生き生きと暮らせる家造りとします。
・こうした考えに基づいた住まいを賃貸住宅ととして創ります。親から子、子から孫へといった家の継承が出来なくなっている今、高齢者の住宅は社会のストックとして、高品質でこれをしっかりと維持管理し、価値を高め次世代に継承していく事はこれからの日本にとって必要不可欠です。
・自然環境の問題提起として、無垢の木を使った木組架構による木の家である事も大切です。尚、地域材(飯能西川材)を使う事も地域の山を活性化し、地域の自然環境は地域で守るといった事から非常に大切です。
・単なる高齢者専用賃貸住宅ではなく、農業を基軸とした地域を構成し、農業に従 事でき、健康に暮らす事を大切にした賃貸住宅とする。
・街と村を繋ぐ山、畑のある里山の景観を構成し、緑豊かな自然環境の中で、地域の中での繋がりを大切に、一緒に農業に従事する事で隣同士の絆を深め、価値観を共有して健康で生き生きと暮らす。
・この高齢者専用賃貸住宅への入居は農業に従事することを条件とする。又、地域 の専業農家からも希望者に入居してもらい一緒に従事する。
・既設の特別養護老人ホーム、在宅リハビリテーション,ケアセンターそしてこれ 等と連携している既設病院も含めた一体とした計画とする。この事は国が進めている在宅介護、在宅診療の施策に対応したものとして大変重要である。
・最寄り品の買い物の利便性を大切に既設コンビニを位置付けする。
・より公共性の高い事業に繋げることで、開発上行政の役割が明確であり、補助金 等の事業支援も得られやすい構造の事業として考えられる。結果としてローコスト住宅の供給が可能となり、環境の整った居住ゾーンとしての提案が可能である。
詳細な資料
ふれあい健康ヴィレッジ開発基本構想に関する詳細な資料は下記よりダウンロードいただけます。